インタープリター・インストラクター養成講座2009
事業報告書&担当者所感

(講座12.森林環境教育 企画の手法 講師:太田祥一)
今年もお蔭さまでインタープリター・インストラクター養成講座を開講することができた。この講座はインタープリター・リーダー養成講座の上位の講座として位置づけてあり、募集要項にも明記してある通り、すでに自然案内人・インタープリターとして活動をしている方々が、これまでの活動経験の成果を出して、インタープリター・インストラクターとしての認定を受ける、という講座である。その成果を、当会では「自ら自然体験イベントを企画立案、実施運営していく」という方法で示してほしいと考えている。リーダー取得後、30日間の自然体験活動を経験してきているならば、その手法さえ知れば、これまでのさまざまな経験から、企画は生み出せるはずなのである。よって、このインストラクター養成講座はインタープリターとしての技術や知識を取得するためのものではない。それは、リーダー養成講座で取得するものであり、インストラクター養成講座では経験豊富なインタープリターに対して成果を求めているのである。
今年は、CONEを通して、文部科学省の小学校長期自然体験活動指導者養成研修としても認定を受けているので、通常のインタープリター・インストラクター講座に学校教育に関する4時間の講座をつけたし、合計27時間の講座となった。参加者は17名。まずまずの人数である。
  
講座1. 学校教育における体験活動の意義(2時間)
講座2. 教育課程と体験活動の関連性(2時間)
講 師 : 大西貞弘(私立清泉小学校教諭、講座1.2共に)
この二つの講座は、学校教育に自然体験活動を積極的に取り入れ実践している当会の会員でもある、大西講師に、実践者として、あるいはインタープリターとして、さらに学校側として自然体験活動指導者に求めたいことを講義していただいた。熱い講義であったが、その詳細報告については以下に譲る。
2009年11月8日 小学校長期自然体験活動指導者養成研修【補助指導者】
また、初日ということで午後一番に、熊川栄嬬恋村長もご来臨賜り、激励のお言葉をおかけくださった。
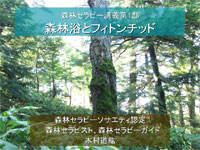  
 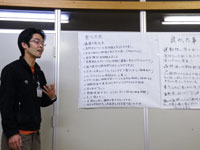 
講座3. 体験プログラム考察「森林セラピー&ハーブクラフト」
講 師 : 赤木道紘(森林セラピスト、アロマテラピーアドバイザー)、
櫻井幸枝(白根高原ラベンダー園、びーがんかふぇ はあとっぷる)
この講座ではスキー修学旅行に来た高校生に対し行う体験学習として、当会が提案するプログラム「森林セラピー&ハーブクラフト」を、まずは体験し、その上で実際に実施するにはどのようにしたら良いのかをグループワーク形式で意見を出し合う。次に小学校長期自然体験活動を意識し、小学校5年生に対して実施するにはどうしたら良いのか…等をグループワークし、最後に各自でまとめて終わる…とした。
体験プログラム「森林セラピー&ハーブクラフト」の内容は、森林セラピスト・アロマテラピーアドバイザーの私木村が、パワーポイントを使って森林浴と植物や香りの効果をプレゼンテーションする。そのあとに地元のラベンダー園経営&栽培者である桜井講師がラベンダーとローズのドライフラワーを使ったハーブクラフトを2種作成するというもの。ラベンダー&ローズのハーブで、室内は濃厚な香りにつつまれていた。3日間のスタートの講座としては、幸先の良いスタートである。
終了後、この体験学習プログラムを高校生にした場合、良かったところと改善すべきところを指摘する2班に分かれてグループワーク。受講者から高校生の修学旅行での体験プログラムとしては講義内容が長く難しいなどの意見が出ていたが、それもそのはず、実際には主催者の思惑は、この体験プログラムを評価してもらうだけではなく、インタープリター・インストラクターと今後名乗っていく受講者に対して、今後当地において成長するであろうマーケットの「森林セラピー」とは何ぞやと、講義していたのである。内容が難しくて当たり前。本来は高校生にする講義ではない。
ラベンダーとローズのハーブクラフトは、これに関してはみんな感激&満足。但し、実際に行うとなるとかなりの指導者の数が必要になるのではないか…などの意見が交わされていた。
この後、この体験学習プログラムを小学生に実施するにはどうしたらよいかをワークショップ。一番初めのワークなので、軽いワークを考えていたのだが、受講生の熱意が大きく、予定の時間をかなりオーバーしてしまった。
 最後に各自でまとめをしていただいて終わり。体験学習プログラムを実施する場合、当然実施側が目的やねらい等の意識を共有しておかなくてはならないのだが、その前にまず、自分ひとりで考えをまとめることができる必要がある。さらに、セラピーの世界では、各自の考えを集めて一つにまとめる必要は無い。自分の考え方を相手に押し付けることは無い。相手の放つものを全て受容するのがセラピストである。今回はセラピーという言葉が講義の中で出てきているので、そのような話をしたうえで、各自でまとめていただいた。 最後に各自でまとめをしていただいて終わり。体験学習プログラムを実施する場合、当然実施側が目的やねらい等の意識を共有しておかなくてはならないのだが、その前にまず、自分ひとりで考えをまとめることができる必要がある。さらに、セラピーの世界では、各自の考えを集めて一つにまとめる必要は無い。自分の考え方を相手に押し付けることは無い。相手の放つものを全て受容するのがセラピストである。今回はセラピーという言葉が講義の中で出てきているので、そのような話をしたうえで、各自でまとめていただいた。
そのあと、自己紹介。さすがこの講座を受けに来るだけの事はある。皆さんとてもお話が上手。来年講師になる人が出てくるかも!
  
講座4. 嬬恋村三原地区の中世〜近代史
講 師 : 松島榮治(嬬恋村郷土資料館名誉館長)
今年は、三原地区でのインタープリテーションを実施するので、事前の学習として、または最終日に自分で企画を作る際の素材の提供として、三原に関する歴史や文化のことを専門家にお話していただく。この講座は嬬恋村の元祖ミスター・インタープリターである松島先生にしていただいた。
松島先生は、地域住民が「この地方には何も誇れるものが無かったんじゃないか」と思ってしまい、その僻地意識によって、ありもしなかった事象をでっち上げてしまったり、伝説を、さも事実であるかのように売り出してしまったりすることがないようにと心配していらっしゃった。
また、調べる資料も、中途半端なものではなく、インタープリターならばとことん追求した、出所のしっかりしたものを選ぶように諭された。私も、配布資料に「嬬恋村で最も古い集落である三原」と書いてしまったことに対して注意を受けている。…実は、嬬恋村誌では三原荘が設置された時は村には集落と呼べる程のまとまった集落は無かったと書いてあったので、よく調べずにそのまま書いてしまったのだ。しかし、鳴尾神社や毛無道のことなどを考えると、確かに門貝のほうが歴史はありそうだ。これには参った。大変失礼いたしました。
  
齊梧講師は登山家として、また登山ガイドとしてのリスクを本当によく勉強して来た人である。リスクマネジメント、指導者の義務、事故発生時の連絡体制、救助要請の知識、指導者の法的責任、保険の知識…などについて一通り勉強し、簡単な演習問題を解いた。その後、実際に登山コースを設定しそこでツアー中に事故が起こったと仮定し、どうするかをワークショップ&発表した。
この講座は、当会の登山ガイド活動に対してどのような意識や心がまえがインストラクターとして必要なのかを、具体的に示し、エクササイズすることができたと思う。
  
講座6. 野外活動における危機管理と対処法の実践
講 師 : 齊梧伸一郎(登山家、レスキュー3インターナショナルほか)
引き続き齊梧さんの講座。登山時の最低携帯必需品の説明、ロープを使ってのレスキューの説明・体験、ツエルトの使い方等を学習した。
しかし、会場を急遽、大会議室から小会議室に変更し狭くなってしまったこともあり、とてもやりにくそうであった。また、齊梧講師にとっては合わせて3.5時間の持ち時間も、足りなかったようだ。ロープワークの練習やレスキュー訓練は、専門的であり、それだけ時間もかかる。今後、この分野はフォローアップ講座を実施することができたらと考えている。
  
講座7. 自然体験活動の理念と実践
講 師 : 小崎昭一(CONEトレーナー、ネイチャーゲームトレーナー)
このインタープリター養成講座は、CONEトレーナーの監修がなければ実施できないことになっている。夏のリーダー養成講座に引き続き、小崎トレーナーにインストラクター養成講座も監修していただいた。
小崎トレーナーが用意してくださった講義資料は、驚くほどわかりやすく、要点を的確に示していた。これほどの講義資料を作れる人は、CONEトレーナーの中にも何人いるのだろうか?と思ってしまった。
自然体験活動と青少年教育に対して、これほど深い情熱と崇高なビジョンを持っている人に私は会った事がない。今回、小学校長期自然体験活動指導者養成研修も兼ねているこの講座のトレーナーに、こんなに相応しい人を私は知らない。しかし、そのハードル設定の高さに、事務局はついていくのに大変なのである。最終的に、当会の実態、地方で頑張っている私達に合わせていただいた。誠にありがたく、深く感謝を申し上げます。
  
講座8. 吾妻地域の木の家
講 師 : 安田滋(一級建築士)
講義を始めるにあたって安田講師は、「前回は木の家のことをあまり知らない自然案内人に対してだったので、誰にでもわかるようにお話しましたが、今回は、インストラクターに対しての講義なので、大学の建築科や専門学校生に対して授業を行うようなつもりで講義をします。専門用語も覚えてください」と仰った。
今回のキーワードは6つ。「せがい造り」「街道沿町屋型と養蚕農家型」「茅葺と石置き屋根」「信州型と新潟型」「近くの山の木」「土蔵造り」。平側、妻側などの建築用語を聞くのも結構面白い。建築のことをよく理解できれば、どの位古いものかわかる。何をしていたのか、何に使っていたのかもわかる。つまりはその地域の暮らしがわかるということである。さらに当時の交通網と照合できれば、文化がどのルートを通って来たのかも考察できるのだ。
この「木の家」の講座はとても興味深い。この不景気で古い木の家の新築建替えが進まないうちに、どんどんやっておかなくてはならない。
  
講座9. インタープリテーション受託事業及び主催事業の基礎講座
講 師 : 大島義夫(登山家、当会副会長)
当会の受託事業・主催事業を一手に引き受け、取り仕切っている大島講師に、実際にどのような流れで事業は実施されているのか?を、昨年に引き続きこと細やかに講義していただいた。当会の事業の手順(受託事業の請書、事業明細、実施目的、人数・参加者レベル・ガイド人数、時間・コース、ガイド料金、各種問い合わせの対応、安全下見、天気予報チェック…)などを学習した後、実際の地形図を使って行程表を作成した。この時も行程表を作るコツとヒントのレクチャーがあった。
この講座を受けることで、受講者はこの会で自分は何をすることになるのかをはっきりと理解できるようになる。とても具体的な講座であり、できればもっと早い段階でやっておきたい講座でもある。
  
講座10. 野外活動における救護技術、応急手当法
講 師 : 小林勝三(あさま治療室、当会副会長)
長らく自衛隊で安全・救護に従事してきた小林講師の講座である。まずは野外活動における救急法、次に冬季に見られる疾患について学習。一通り座学をやってから、いよいよ実際の包帯の使い方、巻き方、テーピングの使い方の練習を行う。ある程度時間を取ったので、ペアになって全員が一通り訓練をすることができた。こういうものはたまにやっておかないと忘れてしまう。聞いただけでは役に立たない。
2日目もたっぷり、8時間の講座が終わった。受講者も疲れも溜まっているはずだが、最期が応急手当の訓練だったこともあり、とても寝てられない状態だったであろうと思う。明日の認定試験に向けて準備するように話したが、帰ってからその元気があるだろうか?
  
  
講座11. 上州三原インタープリテーション
講 師 : 安田滋(一級建築士)、赤木道紘(このガイドさんに会いたい100人)
この講座は、夏のリーダー養成講座の際に実施したかったのだが、夏は突然の大雨で中断してしまったので、インストラクター講座に無理やり入れ込んだ。その分、講座拘束時間は長くなったが、結果的に実際のインタープリテーションを見せることで、自分なりの実施イメージをつかんでくれた受講生もいたようだ。
ネイチャー木村の森林・樹木・植物観と安田講師の木の家・暮らしの解説、そして聞き込み調査からなる当地のお話。この二人がタッグを組んだ上州三原インタープリテーションは、地域案内としてはほとんど最強の感がある。配布資料は、私の案内覚え書きノート、会員でライターの吉井さんの三原の取材記事、黒岩郷土資料館長の古民家えんでぐ資料の三つ。これを読み込んでしまえば、あなたも即席三原インタープリターになれる。
何度やっても三原の集落サイズはほっつき歩くのにちょうどいい。天気も良いし、浅間山も見えて気分が良い。受講生には太田講師から、「目的を持った小旅行として、何か気づいたもの、伝えたいもの等を各自5事象以上持ち帰ること。」という課題が出ている。熱心にメモをとっていたが、「三原集落のインタープリテーションを楽しむことも忘れないで」とも言っておいた。
初代村長のお家から石置き屋根の痕跡、明治屋旅館駐車場から眺める谷あいの集落と草軽電鉄跡。受講者の感激の声が聞こえる。前半、丁寧にやりすぎた感はなかったのだが、やはり二人の専門家が交互にお話し、しかも他にも先生が色々いて、あーでもないこーでもないとインタープリテーションするので、どんどん遅れてしまう。阿弥陀堂あたりでは予定より20分以上遅くなっていた。なのに無理やり篠笛。「う〜さぎ お〜いし か〜のやま〜」
このコースでは後半に大きな樹木が続く。今日はここでは説明している暇がないのに、みんな樹木の立ち姿に見とれてしまって動かない。何か樹木からのメッセージを感じたのだろうか。この講座に来る人は、そういう人が多い。だから最期のケヤキの大木の前では、少しだけ樹木の心に迫ったインタープリテーションをした。心に残ってくれたろうか。
  
講座12. 森林環境教育 企画の手法
講 師 : 太田祥一(群馬県庁)
今回のメイン講師は、この人、群馬県庁の太田講師。最終日の順番は良かった。朝一に実際のインタープリテーションを体験し、実施イメージを得て、さらに気づいたことなどを5つ持ち帰ることで自分なりの感性や表現方法、求めているものことに気づくことができる。そういった「思い」のようなものを沸々と込み上げさせておいて、企画の手順(思い→マーケティング&ポテンシャル→まとめ→コンセプト設定→事業計画)を学習し、それに落とし込んでいくのだ。
企画についてさんざん取り組んできた太田講師は、当初、「企画の講座で5時間では少なすぎる、せめて1泊2日位はなくては…」と仰っていた。もちろん、練る時間が長い方が良い企画になるのだが、この養成講座では企画がメインではあっても、さまざまなエッセンスを受講生に渡したいと思っている。だから、なんとか5時間でおさえていただいた。
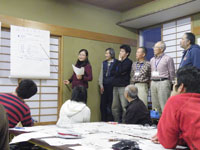 今年の受講生も、いい人材がいる。熱意ある発言が聞こえてきて嬉しい。そして、各班が自分たちの案を発表。 今年の受講生も、いい人材がいる。熱意ある発言が聞こえてきて嬉しい。そして、各班が自分たちの案を発表。
1班「森と音楽の響き 〜Forest concert〜」
2班「Ecoで生活!しゃくなげ My hashi 〜熱帯雨林を救おう!!〜」
3班「Forest Relaxation 〜ストレス発散と癒し〜」
うーん、どうも私の影響が出てしまっているような気が… ま、結構なのですが…
【筆記試験】
あなたは、当会のインストラクターとして、これからどのような「理念」の下、どのように関わっていこうと思っていますか。今回の講座受講をふまえて、具体的な例を上げて200字以上で述べよ。
この試験はそう意図したわけではなかったのだが、結果的に、太田講師の「企画の手法講座」で学んだ企画意図シートにも通じる設問となった。
理念(思い)を、どのようにして具体的な関わり方(事業計画)に結びつけるか
 当会のインストラクターならば、明確に思い画く事ができていないと困るのだ。 当会のインストラクターならば、明確に思い画く事ができていないと困るのだ。
回答の中には、ご自分が実現実施したいことを、当会の活動の中に具体的なビジョンとして落とし込んだ素晴らしい回答もあったが、中には「これまで○○の活動をしてきた。これからも頑張って行きたい」などの、設問に対して回答があっていないものもあった。これまでの活動だけの記述にとどまらず、今回の講座受講を踏まえた何かがほしかったと思う。
しかし、全体的には「理念」も、「これからの関わり方」も十分な記述があったと思う。短い時間で皆さん、よく書き上げてくれたと思う。あのような論文を書くことができる方々と共に活動できることを大変嬉しく思っている。今後がとても楽しみである。
しかし、回収したアンケートを拝読すると、この講座に来ることでインタープリテーションの技術や知識を取得することができる…と思っている受講生が少なくなかったことは残念なことであった。初めにも書いたが、そうではなくて、この講座はこれまで活動経験してきたインタープリテーションの成果を発揮し、認定を受ける講座なのである。ここが間違ってしまうと、また小崎トレーナーに「ハードルが低い」と注意されてしまう!
 それでも、私は当会の養成講座ほど、身の丈にあった講師陣と講義題材で行っているところはないであろう自信はある。世界を飛びまわり啓発活動を行えるインタープリターを育成するつもりはない。遥かなる山や海を越えた世界のものは、私達の体を構成する血や肉に流れていないからだ。(但し現代は世界中の食材が流通しているが…)だから私達は自分たちの体が発する声のまま、自分の知っている地域のことや、自分に聞こえてくる自然の声をそのままお伝えするのだ。 それでも、私は当会の養成講座ほど、身の丈にあった講師陣と講義題材で行っているところはないであろう自信はある。世界を飛びまわり啓発活動を行えるインタープリターを育成するつもりはない。遥かなる山や海を越えた世界のものは、私達の体を構成する血や肉に流れていないからだ。(但し現代は世界中の食材が流通しているが…)だから私達は自分たちの体が発する声のまま、自分の知っている地域のことや、自分に聞こえてくる自然の声をそのままお伝えするのだ。
そして、当会の型で10年我慢してもらわないと取得できない資格などはつくろうとは思わない。感性も表現のあり方も、人それぞれでさまざまだから、自分以外のものにも、自分自身にもかけがえのない価値があるのだ。当会に型を作ってしまったら、アイデアを自らの個性から生み出すことを忘れてしまった、この大不況日本の、1億人のマニュアル人たちのやっていることと同じになってしまう。そういう型やマニュアルを推進しようとする人は、多様でいつも揺らいでいる自然・野外環境のメッセージを伝えるインタープリターには向かないだろう。
だから、当会は多様なものことひとのるつぼであり、揺りかごでありたいと思う。そしてインタープリター養成講座は身の丈通りの小さな器に見合った、満たされた講座を続けて行く。そういったことを、今年は、講座前に講師陣との打ち合わせの中で気がつかせていただくことができた。深く感謝しております。
これで、当会の認めるインタープリター・インストラクターは39名となり、小学校長期自然体験活動指導者養成研修の【全体指導者】は、52名となった。現地のインタープリターの人数も、2013年からの農山漁村交流プロジェクトの準備も、確実に進んでいる。受講生の皆さんの活躍の場をしっかりと作っていくために、事務局も本格的な体制を取っていく覚悟を決めました。今後とも、よろしくご協力ご支援のほどをお願い申し上げます。

平成21年11月20日 嬬恋村インタープリター会 事務局長 赤木道紘
|
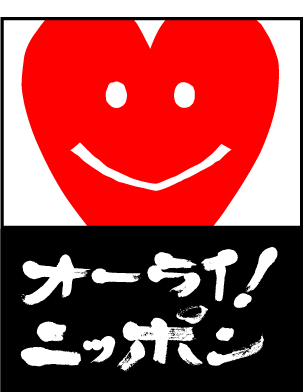 インタープリター・インストラクター養成講座2009
インタープリター・インストラクター養成講座2009

 同会での今年8月に行われたリーダー養成講座の間で、すっかり嬬恋村の自然、村の人々に惹かれてしまった私は、嬬恋村のキャベツ農家のお仕事を見つけ、10月から住ませて頂いて、休みを取っての今回のインストラクター講座の受講でした。
同会での今年8月に行われたリーダー養成講座の間で、すっかり嬬恋村の自然、村の人々に惹かれてしまった私は、嬬恋村のキャベツ農家のお仕事を見つけ、10月から住ませて頂いて、休みを取っての今回のインストラクター講座の受講でした。 今回の講座でも、仕事として現場で長年経験してきた講師陣の講座でのお話は、知識、体験を積み、そして指導者としてやっていく活動は、難しいこともあるが、いかにやりがいのある仕事か、説得力、熱意、迫力のある、自分のモチベーションを上げてくれる、心に響くものでした。それは、多くの受講生を話しに引き込ませたのではないかと思います。
今回の講座でも、仕事として現場で長年経験してきた講師陣の講座でのお話は、知識、体験を積み、そして指導者としてやっていく活動は、難しいこともあるが、いかにやりがいのある仕事か、説得力、熱意、迫力のある、自分のモチベーションを上げてくれる、心に響くものでした。それは、多くの受講生を話しに引き込ませたのではないかと思います。 「こんなに面白い講師の方々の講座を受けられるなんて!ラッキー!」と、思っているのは私だけ?と思っていましたが、一緒に受講していた受講生の方で他でも講座を受けた経験のある方も「レベルが高い!」今回始めて嬬恋村に来た受講生さんも「本田さん(私)が、嬬恋村に惚れてまた来てしまった理由が分かった」と言っていました。
「こんなに面白い講師の方々の講座を受けられるなんて!ラッキー!」と、思っているのは私だけ?と思っていましたが、一緒に受講していた受講生の方で他でも講座を受けた経験のある方も「レベルが高い!」今回始めて嬬恋村に来た受講生さんも「本田さん(私)が、嬬恋村に惚れてまた来てしまった理由が分かった」と言っていました。 嬬恋村に魅入られ、移り住んだ方々、何度も訪れる方々の気持ちがよく分かりました。
嬬恋村に魅入られ、移り住んだ方々、何度も訪れる方々の気持ちがよく分かりました。 その他、自然体験活動の企画作りの手法、ガイドの仕方などの講座で、実際に自分たちで考え作る講座では、アイディアの出し方、考え方の機転、観点の変え方を教えてもらい、また、色々な違う考えの持つ人たちとグループで作り上げていく、難しさ、面白さを体感し、コミュニケーション能力の大切さを感じ、講師による古民家、自然観察の野外でのインタープリテーションでは自分が活動していこうとしている地域の文化、歴史、自然を知ることが自然体験活動を指導する上で自然をもっと深く、上手く、楽しく人に伝えるうえで大切で、多方面での知識をもっと知ることの大切さを再び認識しました。
その他、自然体験活動の企画作りの手法、ガイドの仕方などの講座で、実際に自分たちで考え作る講座では、アイディアの出し方、考え方の機転、観点の変え方を教えてもらい、また、色々な違う考えの持つ人たちとグループで作り上げていく、難しさ、面白さを体感し、コミュニケーション能力の大切さを感じ、講師による古民家、自然観察の野外でのインタープリテーションでは自分が活動していこうとしている地域の文化、歴史、自然を知ることが自然体験活動を指導する上で自然をもっと深く、上手く、楽しく人に伝えるうえで大切で、多方面での知識をもっと知ることの大切さを再び認識しました。 そして、実際に木の葉や植物を使った森林療法、ハーブのクラフト作りの体験講座では、体験をする参加者の年齢によって物を使った伝え方、楽しませ方、気づかせ方を変える難しさを考えさせられ、また具体的な森林療法や香り体験による精神や身体に及ぼす効果の科学的データを使ったり、実際に楽しめる物を使い伝えるのは、多くの人や子供たちに自然体験のすばらしさを理解してもらう上で、入り口として大変便利だと再確認しました。
そして、実際に木の葉や植物を使った森林療法、ハーブのクラフト作りの体験講座では、体験をする参加者の年齢によって物を使った伝え方、楽しませ方、気づかせ方を変える難しさを考えさせられ、また具体的な森林療法や香り体験による精神や身体に及ぼす効果の科学的データを使ったり、実際に楽しめる物を使い伝えるのは、多くの人や子供たちに自然体験のすばらしさを理解してもらう上で、入り口として大変便利だと再確認しました。 今回私にとってこの講座で良い収穫になったことは、8月にお会いした方々に再会でき盛り上がったこと。沢山経験をつまれ、色々な方面で活躍されている受講生の方々の意見、お話が聞け刺激になったこと。目標としたい、素敵な講師陣の講義を受け、お話しすることができ、自分の知識、体験のレベル、立ち位置を確認し、これから具体的に何を学び実践していくべきか知れたこと。そして同じ方向に向いている、自分と近い年代の方々と出会い、繋がりを持て勇気が沸いて元気をもらえた事、です。
今回私にとってこの講座で良い収穫になったことは、8月にお会いした方々に再会でき盛り上がったこと。沢山経験をつまれ、色々な方面で活躍されている受講生の方々の意見、お話が聞け刺激になったこと。目標としたい、素敵な講師陣の講義を受け、お話しすることができ、自分の知識、体験のレベル、立ち位置を確認し、これから具体的に何を学び実践していくべきか知れたこと。そして同じ方向に向いている、自分と近い年代の方々と出会い、繋がりを持て勇気が沸いて元気をもらえた事、です。




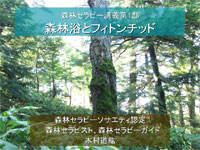



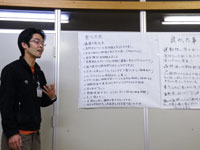

 最後に各自でまとめをしていただいて終わり。体験学習プログラムを実施する場合、当然実施側が目的やねらい等の意識を共有しておかなくてはならないのだが、その前にまず、自分ひとりで考えをまとめることができる必要がある。さらに、セラピーの世界では、各自の考えを集めて一つにまとめる必要は無い。自分の考え方を相手に押し付けることは無い。相手の放つものを全て受容するのがセラピストである。今回はセラピーという言葉が講義の中で出てきているので、そのような話をしたうえで、各自でまとめていただいた。
最後に各自でまとめをしていただいて終わり。体験学習プログラムを実施する場合、当然実施側が目的やねらい等の意識を共有しておかなくてはならないのだが、その前にまず、自分ひとりで考えをまとめることができる必要がある。さらに、セラピーの世界では、各自の考えを集めて一つにまとめる必要は無い。自分の考え方を相手に押し付けることは無い。相手の放つものを全て受容するのがセラピストである。今回はセラピーという言葉が講義の中で出てきているので、そのような話をしたうえで、各自でまとめていただいた。





























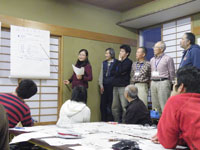 今年の受講生も、いい人材がいる。熱意ある発言が聞こえてきて嬉しい。そして、各班が自分たちの案を発表。
今年の受講生も、いい人材がいる。熱意ある発言が聞こえてきて嬉しい。そして、各班が自分たちの案を発表。 当会のインストラクターならば、明確に思い画く事ができていないと困るのだ。
当会のインストラクターならば、明確に思い画く事ができていないと困るのだ。 それでも、私は当会の養成講座ほど、身の丈にあった講師陣と講義題材で行っているところはないであろう自信はある。世界を飛びまわり啓発活動を行えるインタープリターを育成するつもりはない。遥かなる山や海を越えた世界のものは、私達の体を構成する血や肉に流れていないからだ。(但し現代は世界中の食材が流通しているが…)だから私達は自分たちの体が発する声のまま、自分の知っている地域のことや、自分に聞こえてくる自然の声をそのままお伝えするのだ。
それでも、私は当会の養成講座ほど、身の丈にあった講師陣と講義題材で行っているところはないであろう自信はある。世界を飛びまわり啓発活動を行えるインタープリターを育成するつもりはない。遥かなる山や海を越えた世界のものは、私達の体を構成する血や肉に流れていないからだ。(但し現代は世界中の食材が流通しているが…)だから私達は自分たちの体が発する声のまま、自分の知っている地域のことや、自分に聞こえてくる自然の声をそのままお伝えするのだ。